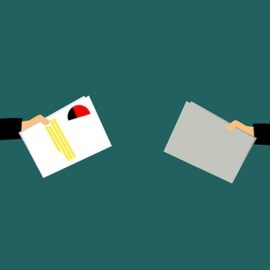成功循環モデルから学ぶ④~組織開発(OD)の実践って、どうするの?-197~
メンタル・モデルの克服に有効なアプローチとして、前回のODメディアでは「シナリオ・プランニング」を紹介しましたが、今回は「対話」です。P.センゲは、ハノーバー保険の事例を取り上げています。ハノーバー保険は、権威主義的というパラダイムで組織が運営されていました。それは、「経営の方針を決め、必要なリソースを組織化し、間違いがなく仕事が遂行されるよう管理する」というものです。経営管理では至極当然のようですが、しかし、このようなやり方は硬直的かつ依存的であり、組織の個々の部署や個人が変化に主体的に対応するような動きになっていませんでした。そこでハノーバー保険は、この階層制の権威主義的価値観を刷新し、仕事がもっと人間性に調和したものになるためには新しい価値観を見出すことが必要と考えたのです。そして、従来のメンタル・モデルから脱却するには、「開放性」と「メリット」が重要であると捉えました。「開放性」とは、対面での会議などで人々が支配されている心理について言及することができる環境をつくることです。ODメディアで度々紹介しているW.シュッツ風に言えばオープンネス、A.エドモンドソン風に言えば心理的安全の確保です。「メリット」とは、その組織の最善の利益を念頭において決断を下すというものです。
さて、このような考えに基づく取り組みは、これが進んでいくと当然のことながら「みんな異なる世界観を持っているのだから、それを大っぴらにしてもっと建設的な議論ができれば、意思決定のプロセスももっと健全になるはずだ」ということに行きつきます。しかし、ほとんどの人はこのことに対して困難さを感じてしまいます。それは、いまでは多くの研究者の研究で分かっていますが、人々の心にある「防衛機制」という大きな壁・思考の箍があるからです。要するに、あることに熟練した人たちは、自分の持っている信念体系すなわちメンタルモデルを探られるのが嫌なのです。アージリスは、そのような人たちのことを「熟練無能力者」と名付けました。対話という技術は、アージリスを始め、E.シャイン、W.シュッツ、R.キーガンなどが詳しくその技術を紹介してくれていますが、いずれもオープンな議論や思考・行動変容を妨げているのは自分の中にあるメンタル・モデル(氷山思考、自己解釈の枠組みなど、いろいろな言い方がある)が暴かれることに対する不安です。柔軟な・合理的な思考ができない人たちは、みんなそれ「自分だけのメンタル・モデル」にしがみついているのです。対話についての技術解説はここでは割愛しますが、対話によって固い思い込み(メンタルモデル)が解凍していくプロセスを描いている映画があります。アメリカ映画の秀作である「12人のいかれる男」がそれです。Amazonでレンタルですが見ることができます。
メンタル・モデルを克服するためのアプローチとして「シナリオ・プランニング」と「対話」という方法を紹介しましたが、現実の経営や組織運営の中でメンタル・モデルをまず克服しなければならないのは、経営幹部です。彼らこそ、自己省察と探求の技術を身に付ける必要があります。ところが、これが至難の業なのです。なぜかといえば、彼らはその組織が成長していく過程で、その成功方程式を身に付けてきた人たちなのです。だからこそ、組織の上位階層に上り詰めたのです。そのような人たちが、自ら進んで自分のメンタル・モデルを変えようとするかといえば、それはNoなのです。シェルのようなそもそも複合的で、複雑な意思決定プロセスをマネジメントしてきた組織は、むしろその困難さを理解しているということで、メンタル・モデルを見直していくプロセスを導入するのは、他の組織に比較し却って容易かったといえます。現代の日本でいえば、東芝という名門企業が混乱し、臨時株主総会(2022年3月)でも会社側提案がすべて否決されるという失態を招いています。東芝の経営層は、東芝という組織が持っているメンタル・モデルを明らかにして、このような価値基準をどのように変えていくかを明確にしていないようです。臨時株主総会で発表されたことは、会社二分割による収益向上策であり、なぜこの案が東芝のこれまでの思考と行動を変えることができるのかということに対して言及されていないようです。結果、出席した株主たちのメンタル・モデルに刺さるような提案になっておらず「否決」という憂き目にあったようです。
さて、P.センゲのメンタル・モデルの管理に話を戻すことにしましょう。メンタル・モデルを変えていくには、ビジネスの前提・問題点に関する認識と、「シナリオ・プランニングと対話」を効果的に進めるために求められるコミュニケーションという対人関係上の技術が必要です。これがなければ、人々のメンタル・モデルの変革は実践できません。このような実践過程におけるメンタル・モデルのマネジメントで勘違いされることは、新しいメンタル・モデルを策定して、それを浸透させていけば、組織のメンタル・モデルが変わっていくという間違った幻想です。ハノーバー保険でメンタル・モデルの変革をリードした当時のCEOであるビル・オブライエンは「選定されたメンタル・モデルなど我々にはない。あるのは、メンタル・モデリングの哲学だ。もしも、のこのこと現場に出かけていき、当社には○○というメンタルモデルが今後必要だ、などといいだしたら厄介なことになる」と語っています。留意しておきたいことは、合意や調和が目指すゴールではないということです。いくつものメンタル・モデルがあっていいのです。しかし大切なことは、どのようなメンタル・モデルであれ、来るべき様々な状況に照らして吟味され、検討される必要があるということです。組織のあらゆるメンバーに必要な態度は「それはこれからも必要なことなのか」と問う「真実へのこだわり(P.センゲ)」であり、それは自己マスタリー(絶え間ない自己啓発・自己成長)の当然の結果として存在しなければならないのです。そのためには、逆説的でもありますが、真実全体を知りえることはできないという理解も必要です。みんなの調和がゴールではありませんが、議論のプロセスが効果的でうまくいけば自然と調和に向かい、納得感のあるメンタル・モデルが生成してくるでしょう。成功循環モデルの「思考の質」は、「関係の質」だけではなく置かれている環境や体験から形成されるメンタル・モデルに強い影響を受けるのですね。(続く)
この記事の書き手はJoyBizコンサルティング(株)波多江嘉之です。